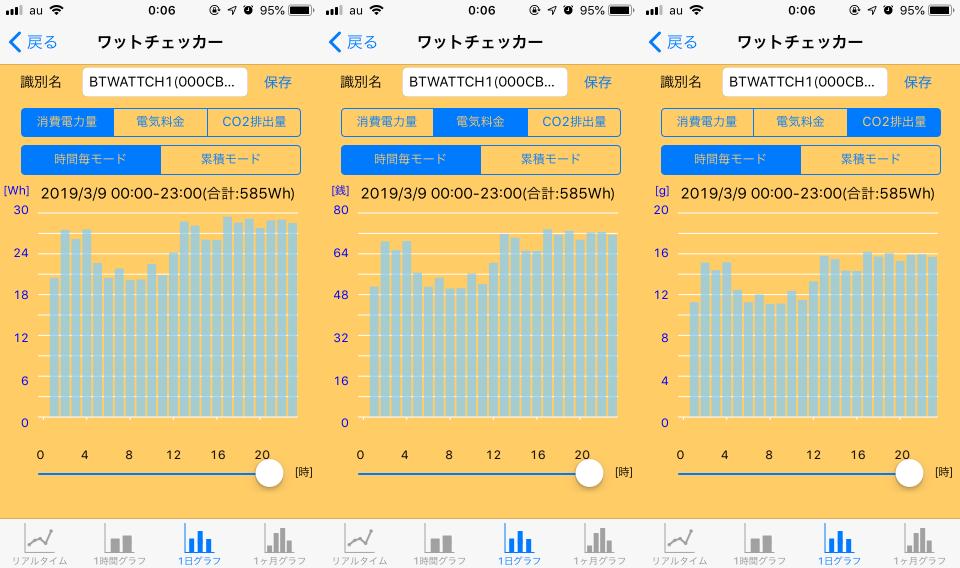林哲司×土岐麻子のシティ・ポップ談義 洋楽が日本語ポップスに与えた影響を辿る
林哲司、土岐麻子

昨今のシティ・ポップの海外での人気沸騰を象徴する一曲、松原みきの「真夜中のドア ~Stay With Me~」(1979年)の作曲をはじめ、70年代から数々の大ヒットを手がけた林哲司。昨年(2021年)リリースされた彼の洋楽遍歴をまとめたコンピレーションCD『melody of memory – City Pop of Tetsuji Hayashi Selection』には、洋楽の名曲群の最後にボーナストラックとして、土岐麻子をシンガーとして起用した新録音曲「ナイト・イン・ニューヨーク」(エルボウ・ボーンズ&ザ・ラケッティアーズのカバー)が収録されていた。【画像を見る】史上最高のベーシスト50選シティ・ポップのオリジネイターである林と、林が手がけた数々のヒット曲を子供の頃から聴いて育った世代である土岐。70年代から2020年代にかけて、自分たちは洋楽にどう影響を受け、それを日本語のポップスにどう落とし込むかを考えてきたのか。2人の対談は、シティ・ポップの枠を超え、日本のポップス史の一面が浮かび上がるものにもなった。 * * *─昨年12月にリリースされたコンピレーションCD『melody of memory – City Pop of Tetsuji Hayashi Selection』が好評です。音楽家であり洋楽リスナーとしても林哲司さんのルーツとなった楽曲が60年代から80年代に至るまでセレクトされていて、80年代半ばくらいまでの「洋楽が強かった時代」のムードを感じました。土岐さんはこういう曲をラジオやCDで聴きながら育った世代と言えると思いますが、どんなふうに林さんの選曲を聴かれました?土岐:すごくワクワクしました。知っている曲も知らない曲もありましたけど、私が原体験として感じた音楽の輝きがすごく詰まっていていると感じました。CDでの発売でしたけど、カセットテープにしたくなりましたね(笑)。林:僕も自分でカセットの時代からプライベートで楽しむようにコンピレーションを作ったりしていましたからね。結果的に曲を選んでみて、いわゆるブルーアイドソウル的な、白人と黒人の両方のエッセンスがあるものが自分は好きだなとあらためて感じました。─選曲には60年代のクラシックス・フォーなども含まれていますよね。土岐さん世代は、もちろんリアルタイムではないですが90年代に「ソフトロック」のリバイバルとしてこういうサウンドをくらった世代だと思いますが。土岐:まさにその通りです。みなさんそうだと思うんですけど、自分が生まれた年前後の音楽って無意識に体のなかに入っているんですよ。大学生くらいになって、「あれはいったい何だったんだろう?」と、そういう記憶を発掘して聴き直すみたいなことがよくありました。私の世代だと、70年代、さらにさかのぼって60年代の音楽への憧れが大学生の頃には強かった。物心つく前に浴びていた音楽を、自分が音楽をやるようになってからくらったという。林:お父さん(サックス奏者の土岐英史氏)の影響もあったんですか?土岐:家では常に音楽はかかっていました。ブラックミュージックが多かったですね。曲名は知らなくてもすごく好きな曲というのは結構ありました。後から考えたらスティーヴィー・ワンダーやチャカ・カーンだったんですが。AORの曲もかかっていました。─林さんはCDでもAORの代表格であるボズ・スキャッグス「ジョジョ」をセレクトされています。作曲家として本格的に仕事を始められたタイミングもAOR登場と重なっていますよね。林:やっぱり、ボズの影響は大きかったですね。AORという言葉が日本で認識されたのは、彼のアルバム『シルク・ディグリーズ』(1976年)あたりが起源だったと思います。その頃に、自分が作曲家として作りたい音楽と好きで聴いている音楽がすごくクロスしたという感覚はありました。でも、メロディがある音楽や、コードワークに工夫が凝らされている音楽が好きだという資質は、それ以前からずっとあるんです。それに、土岐さんはお父さんがかけていた音楽の影響を自然に受けていたように、僕も同じように年の離れた兄たちが60年代に聴いていた洋楽や日本の歌謡曲が同時に耳に入ってきてて、のちのち自分が日本語のポップスを書く上での影響になったのかなと思うところもありますね。土岐:私も80年代のアイドル全盛期に中学生だったので歌番組をよく見ていました。大学生くらいであらためて当時の歌謡曲を聴いてみて、すごくかっこよかったり、粋なことをやっているんだなとびっくりしましたね。洋楽からの影響をすごく挑戦的に受け入れているアレンジで、様式美みたいなAメロ、Bメロ、サビ、大サビがあった。今、私が歌詞のストーリーを紡ぐ時も、A→B→サビで情緒的な流れをつけたり、起承転結をつけたりするのがすごく大事なんです。日本のポップスのいいところであるその物語性を活かしつつ、アレンジでは攻めていきたいというのは、あの頃の影響だと自覚しています。林:ちょうど80年代くらいにA→B→C(サビ)構成というのが日本のポップスで形作られたんですよ。その前だと、A→Bくらいで、Bがサビにあたるものが多かった。サビへのつなぎの役割をするBメロというのは、あまりなかったんです。たぶん、僕らがAORとかアメリカの音楽に影響受けた世代の登場で、構成要素が増えて、もう少しメロディのパーツが多くなった気がします。土岐:じゃあ、A→B→C構成というのは洋楽からの影響だったんですか。林:かなり強かったと思います。ただ、今の若い人たちが当時のシティ・ポップや歌謡曲に触れて、どこが洋楽とは違うと感じるのかというと、AやB、Cとのつなぎの部分だと思うんです。歌謡曲のほうがもうちょっと細かさがそこにある気がします。あの当時、僕ら作曲家も作詞家もミュージシャンもアメリカ音楽の影響を受けて吸収するものはすごく多かったけど、手作り感は日本とアメリカでは若干違っていた。海外の製品を学んで日本で作った家電製品みたいな、微妙なニュアンスでパーツとパーツをつないで曲をまとめ上げたことで生まれた日本製ならではの良さ、みたいなものがもしかしたらあるのかも。今、日本の80年代シティ・ポップが海外で人気だと聞いた時も、なぜ日本の方に関心がきてるのか疑問でもあったんです。もしかしたら、日本人の作る哀愁感とかメロディ運びがアメリカ人とはちょっと違うのを、世界の人たちが感覚的に感じ取ってるのかな。土岐:哀愁感という言葉には、なるほど、と思います。演歌からフォークを経由した流れなのか、湿度というかあまりカラッとはしていない心を歌いたいという感じが日本のポップスにはあると思うんです。カラッとした洋楽寄りのアレンジに対して、メロディや各パーツの役割がちょっとセンチメンタルな気持ちや濡れたような感情を表現するようなものになっている。Bメロでちょっとしっとりして内省的になって、サビで大きくなる、みたいな(笑)。それが今「和風」と感じられるテイストになっているのかもしれません。
次ページは:シティ・ポップと「英語フレーズ」最終更新:Rolling Stone Japan